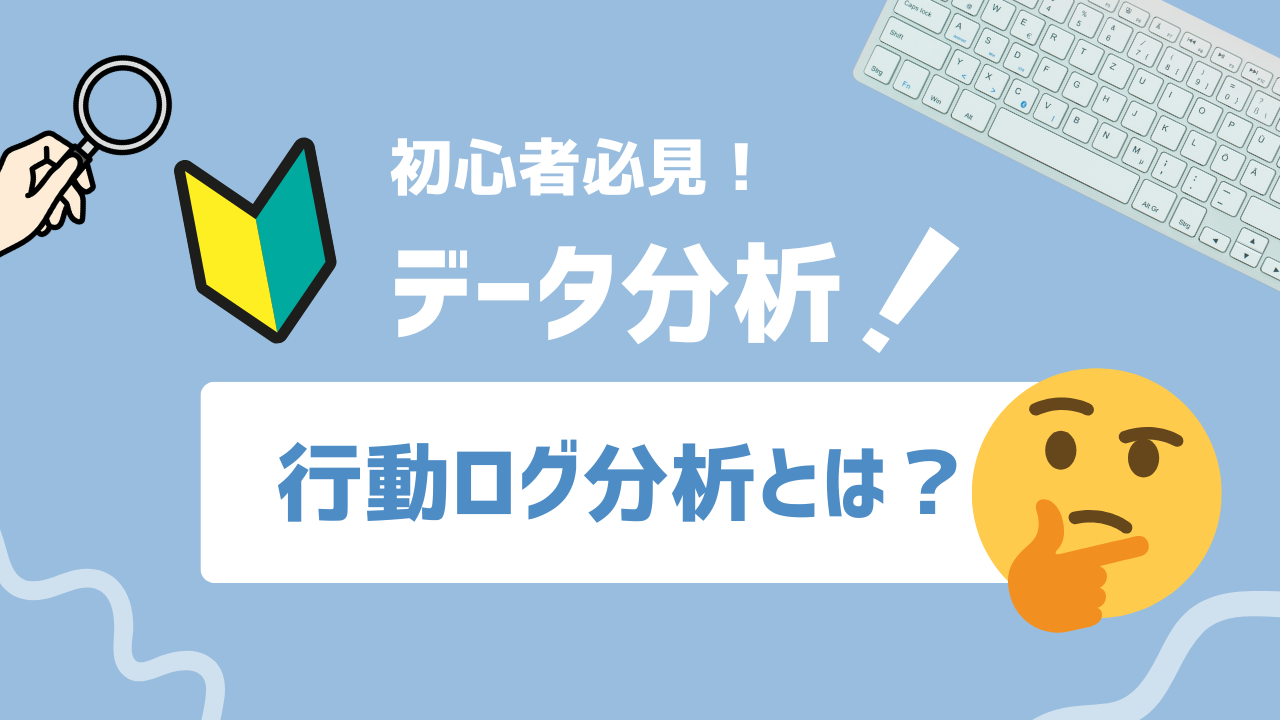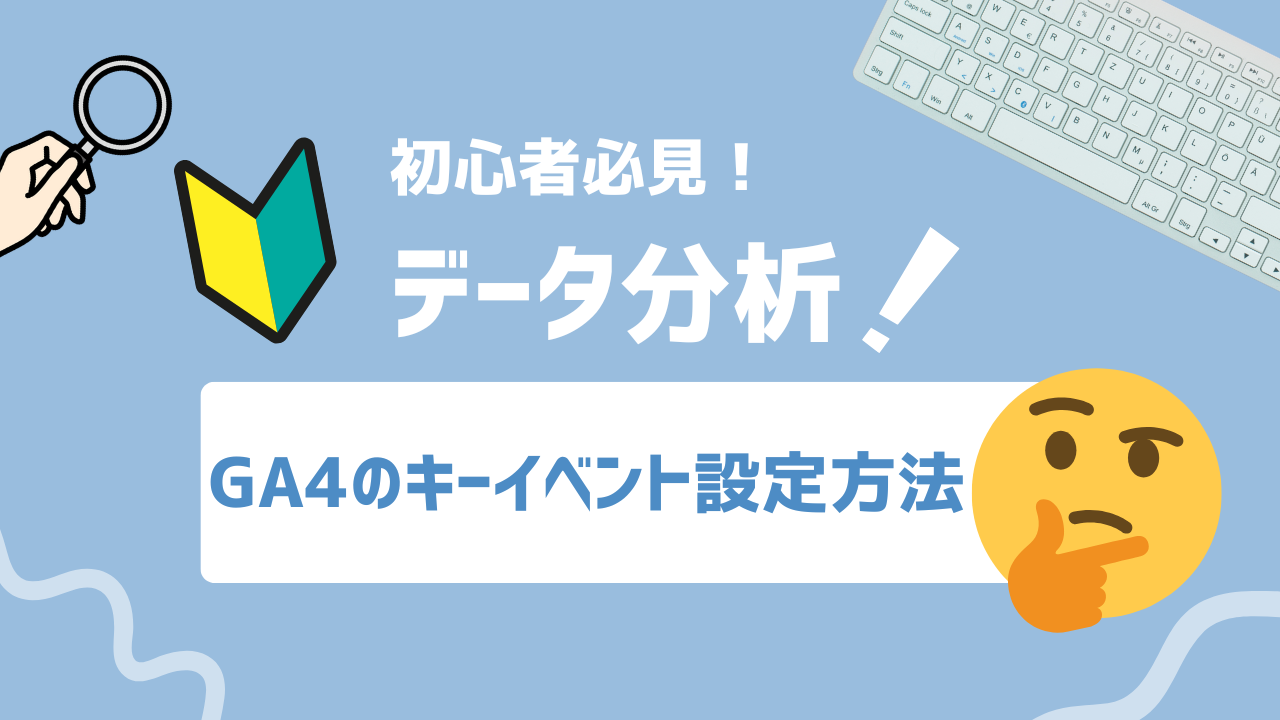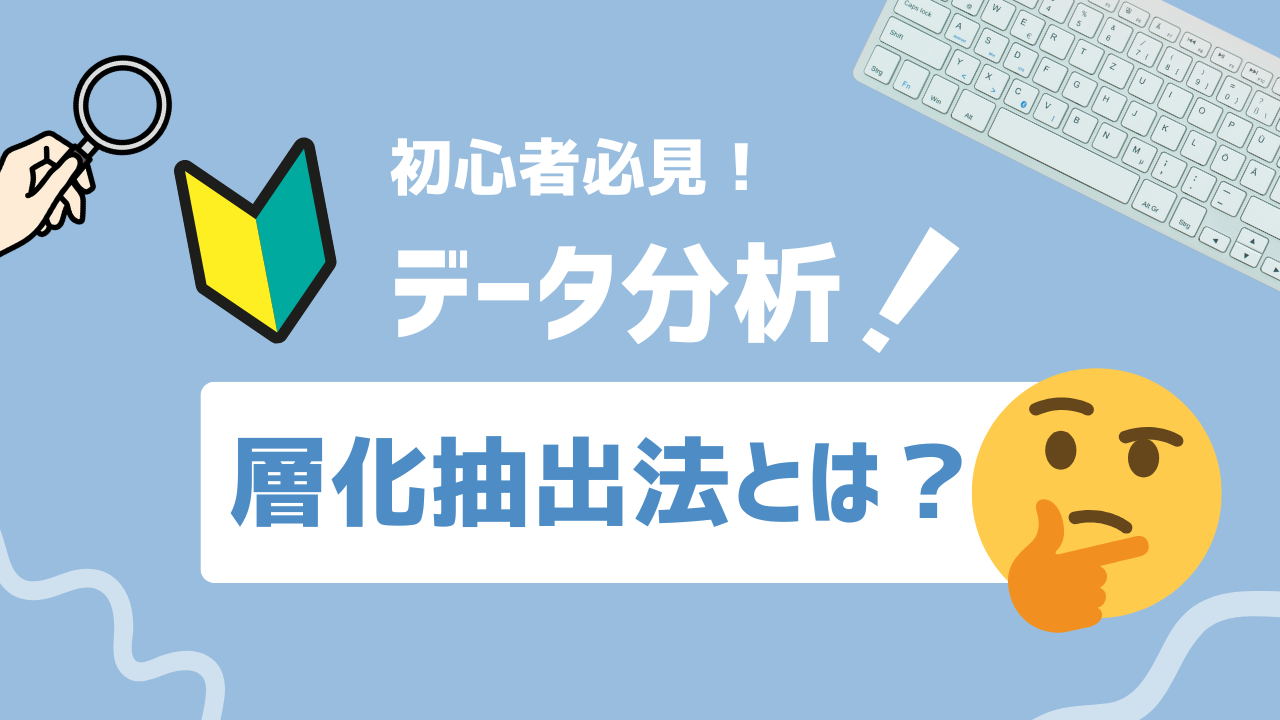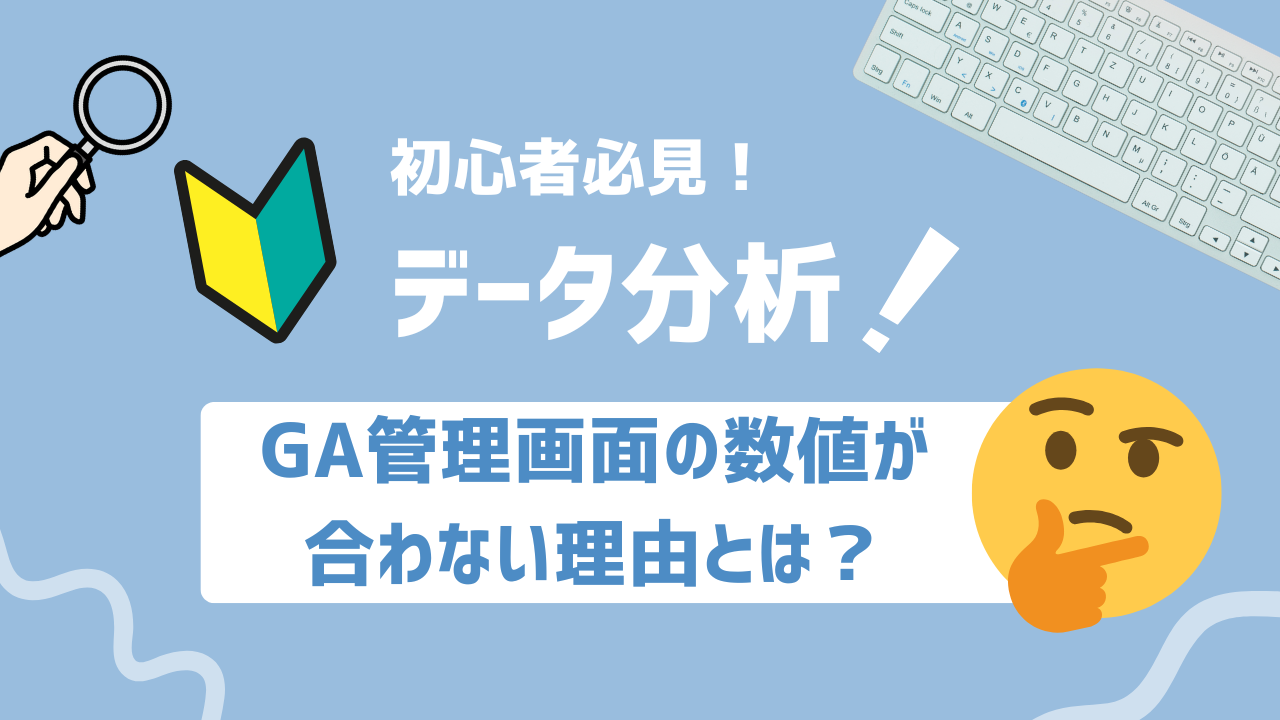【2025年最新】回遊率とは?Webサイトのユーザー行動を最適化する鍵を徹底解説

Webサイトの成果を左右する要素の1つに「回遊率」があります。回遊率は、ユーザーがWebサイト内でどれだけ多くのページを閲覧したかを示す指標で、ページ間の移動がどれほど活発に行われているかを把握できます。訪問者が1ページだけを見て離脱してしまうのではなく、複数ページを巡回してくれるかどうかは、サイトの設計や導線が適切かを測る重要な判断材料となります。
本記事では、回遊率の意味や基本的な計算方法、直帰率や離脱率との違い、そして実践的な改善策までをわかりやすく解説していきます。
目次
回遊率とは?回遊率の意味と基本的な考え方
回遊率はサイト内の“滞在行動”を示す指標
回遊率とは、ユーザーがWebサイト内で複数ページを閲覧した割合を示す指標です。具体的には、1セッションあたりのページビュー数(PV)をもとに算出されることが一般的で、サイト内の導線が適切か、コンテンツの魅力があるかを測る参考になります。
たとえば、回遊率が3.2であれば、1人のユーザーが平均して3ページ以上を閲覧していることになります。
回遊率の基本的な算出方法
回遊率は以下の式で簡易的に把握できます。
回遊率=PV数÷セッション数
たとえば、1日でページビュー数(PV)が1,000、セッション数が400だった場合、回遊率は2.5(=1000 ÷ 400)となります。これは、1回の訪問あたり平均して2.5ページ閲覧されているという意味です。
回遊率の目安と確認方法
回遊率を効果的に改善するには、まず自社サイトの現状を把握し、他サイトと比較して高いか低いかを判断することが重要です。このセクションでは、一般的な回遊率の目安と、Google Analyticsを使って実際に数値を確認する方法について解説します。
回遊率の目安(参考値)
回遊率の目安は、業種やサイトの目的によって異なりますが、一般的にはセッションあたりのページビュー(平均ページビュー数)で2.0〜3.5程度が標準的とされています。
| サイトタイプ | 平均的な回遊率(ページ/セッション) |
| コーポレートサイト | 2.0〜3.0ページ |
| ECサイト | 3.0〜5.0ページ |
| オウンドメディア | 2.5〜4.0ページ |
| BtoBサービスサイト | 2.0〜3.5ページ |
逆に、5ページ以上の回遊が続く場合は、コンテンツの深さや導線設計が機能しており、ユーザーの関与度が高い状態と考えられます。
Google Analyticsを用いた確認方法

回遊率はGoogle Analyticsを使って簡単に確認できます。厳密には「回遊率」という指標は存在しませんが、「ページビュー数」や「セッションごとの平均ページビュー」などから回遊状況を間接的に把握することができます。
- Google Analyticsにログインします。
- 左側のメニューから「レポート」を選択します。
- 「ユーザー」セクションをクリックし、その中の「ユーザー属性」を選びます。
- 「オーディエンス」を開くと、セッション数やユーザー数、ページビューなどの指標が一覧で表示されます。
- この中にある「ページ/セッション」という項目が、1回のセッションあたりにユーザーが閲覧したページ数、つまり回遊率に相当する指標です。
この数値が高いほど、ユーザーが1回の訪問で多くのページを閲覧していることを意味します。コンテンツの関連性や導線のわかりやすさを示す重要なデータとなるため、定期的に確認しておくとよいでしょう。
回遊率が使われる主な場面
コンテンツの導線改善や内部リンク設計に活用
回遊率は、ユーザーがサイト内をどれだけスムーズに巡回できているかを示す指標で、内部リンクやUI設計の効果検証に活用されます。たとえば、記事本文中のリンクから関連記事へ移動しているか、カテゴリーページの構成が直感的か、商品ページからカートや購入ガイドにスムーズに遷移しているかなどを判断する材料になります。こうした情報は、リンク設計の改善やナビゲーション最適化に直結します。
メディア運営やECサイト運営に欠かせない視点
回遊率は、サイトの種類によって特に重視される場面があります。
たとえば、オウンドメディアでは関連記事の閲覧が増えることで滞在時間が伸び、エンゲージメント向上につながります。ECサイトでは、ユーザーが複数の商品やカテゴリを比較しやすくなり、購入検討の促進に効果的です。会員制サイトでは、マイページやFAQへの移動がスムーズであれば、継続利用や自己解決率の向上に貢献します。
回遊率を高めるための具体的な改善策
内部リンクとUI配置を最適化する
回遊率を高めるには、ユーザーが次に読むべきページを自然に見つけられる仕組み作りが欠かせません。本文中に文脈に合った内部リンクを配置することで、読者は興味のある情報にスムーズに遷移できます。
また、記事末尾に「この記事を読んだ人におすすめ」などの関連記事セクションを設ける、サイドバーやパンくずリストなどのナビゲーションUIを整理するといった方法も有効です。こうした設計により、ユーザーが迷わず他ページへ進む体験が整います。
コンテンツ設計を検索意図中心に再構築する
ユーザーの回遊を促すには、単にリンクを張るだけでなく、コンテンツそのものが一連の流れで読まれるように設計されていることが重要です。
具体的には、検索意図を深掘りして、関連情報・前提知識・次に知りたくなる情報まで網羅した構成にすることで、ユーザーの興味が途切れにくくなります。また、章ごとに段階的に知識が深まる設計にすることで、「この続きをもっと知りたい」という内発的動機からの回遊が生まれやすくなります。
回遊率が高いことで得られるメリット
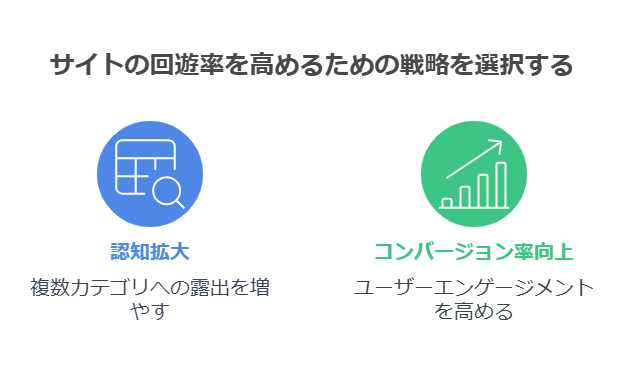
複数カテゴリや商材への認知拡大につながる
ユーザーが複数カテゴリや関連商品を回遊することで、「最初は知らなかった商品・サービス」にも接触しやすくなります。クロスセル・アップセルの機会が増えるという実利的なメリットがあります。
コンバージョン率の向上が期待できる
複数ページを閲覧するユーザーは、情報を比較・検討しながらより深く関心を持っている可能性が高いため、CV(コンバージョン)につながりやすくなります。特にBtoBサイトや比較検討型サービスのサイトでは、詳細な事例ページやFAQなどを経由してCVに至るケースが多く、回遊率の高さが成果に直結することがあります。
回遊率に関するよくある質問(Q&A)
回遊率を上げるための具体的な方法は?
記事末尾に「読者の次の行動」を明示するCTAリンクを設置する
記事を読み終えたユーザーが次にどこへ進めばよいかを明確にするために、記事の末尾に「次に読むべき記事はこちら」や「このテーマに関連する解説はこちら」といったリンクを設置します。
たとえば、SEOの基礎を解説した記事の末尾に「キーワード選定の実践ガイド」へのリンクを配置することで、ユーザーを自然な流れで次のページへと誘導できます。
本文中に自然な形で内部リンクを挿入する
関連記事を並べるだけでなく、文章の流れに沿って他の記事へのリンクを差し込むことで、ユーザーが違和感なく次のコンテンツへと興味を持ちやすくなります。
たとえば、「検索意図を把握するにはユーザー行動の分析が重要です」という一文に対し、「ユーザー行動分析」に関する記事へのリンクを埋め込むことで、読者の関心に応じた自然な回遊を促すことができます。
カテゴリとタグを整理し、サイト構造を最適化する
カテゴリやタグが整理されていないと、ユーザーが興味のある情報を見つけづらくなります。上位カテゴリ(例:マーケティング施策)と下位カテゴリ(例:SNS、広告、SEO)を明確に分け、記事ページにカテゴリリンクやタグナビゲーションを設置することで、サイト内の移動がしやすくなります。
これにより、ユーザーは自分の関心に合わせて複数のページを巡回しやすくなり、自然と回遊率の向上につながります。
回遊率が低い場合の対策は?
回遊率が低い場合、以下のような原因が考えられます。
| 原因 | 対策例 |
| コンテンツが浅く満足度が低い | 情報量を増やす、事例や図表を追加 |
| 次に読むべきページへの誘導が弱い | 関連リンクやタグ、CTAを追加 |
| トップページへの依存が強い | ランディングページ単位での導線設計を見直す |
| モバイル対応が不十分 | レスポンシブ対応、モバイルUI改善 |
| サイト構造が複雑で迷いやすい | サイトマップやカテゴリの見直し |
他の指標と比べて回遊率の重要性は?
回遊率は、ユーザーがどれだけWebサイト内を巡回しているかを表す指標であり、以下の点で重要です。
| 指標 | 意味 | 回遊率との違い |
| 直帰率 | 最初の1ページだけ見て離脱 | 回遊率が高ければ直帰率は下がる傾向 |
| 平均セッション時間 | サイト滞在時間の長さ | 回遊率と相関するが内容には依存 |
| CVR(コンバージョン率) | 購入や問い合わせの割合 | 回遊率が高い=CV導線に乗っている可能性 |
つまり、回遊率はコンバージョンに至る前段階(情報収集)の活性度を示す中間指標として活用できます。
回遊率が高いとどのような効果が期待できるか?
回遊率が高いということは、ユーザーが複数のページを見ている状態です。そこから得られる効果は以下のとおりです。
- ユーザーの関心が高いことの証明
有益な情報があると判断されているため、ブランドやサービスへの信頼感向上が期待できる。 - SEOの評価向上
Googleはユーザー行動(回遊、滞在)を間接的に評価しており、回遊率の高さは評価ポイントとなる可能性がある。 - CVへの寄与
商品比較・理解・事例確認など、CVにつながる情報に複数触れる機会が増える。
回遊率とユーザー体験(UX)の関係は?
回遊率は、ユーザー体験(UX)の質を間接的に測る指標として活用できます。ユーザーが複数のページをスムーズに閲覧している場合、それはサイト構造やコンテンツ設計が直感的で、次の行動を取りやすい状態にあることを示しています。つまり、回遊率が高いほど、UXが良好である可能性が高まります。
一方で、ページ構成がわかりにくかったり、リンクが適切に配置されていなかったりすると、ユーザーは目的の情報にたどり着けず、早期に離脱してしまう傾向があります。たとえば、1ページの中で情報が完結していても、ユーザーが「もっと知りたい」と思って別ページに進むかどうかは、そのサイトのUX設計の質によって左右されます。
まとめ
回遊率は、ユーザーがWebサイト内をどれだけ深く巡回しているかを示す重要な指標であり、導線設計やコンテンツ構成の最適化に直結します。直帰率や離脱率と組み合わせて分析することで、より正確なユーザー体験の把握が可能になります。単に数値を上げることだけを目的にするのではなく、「意味のある回遊」を設計することが、成果につながるWebサイトづくりの第一歩といえるでしょう。
 ポスト
ポスト シェア
シェア