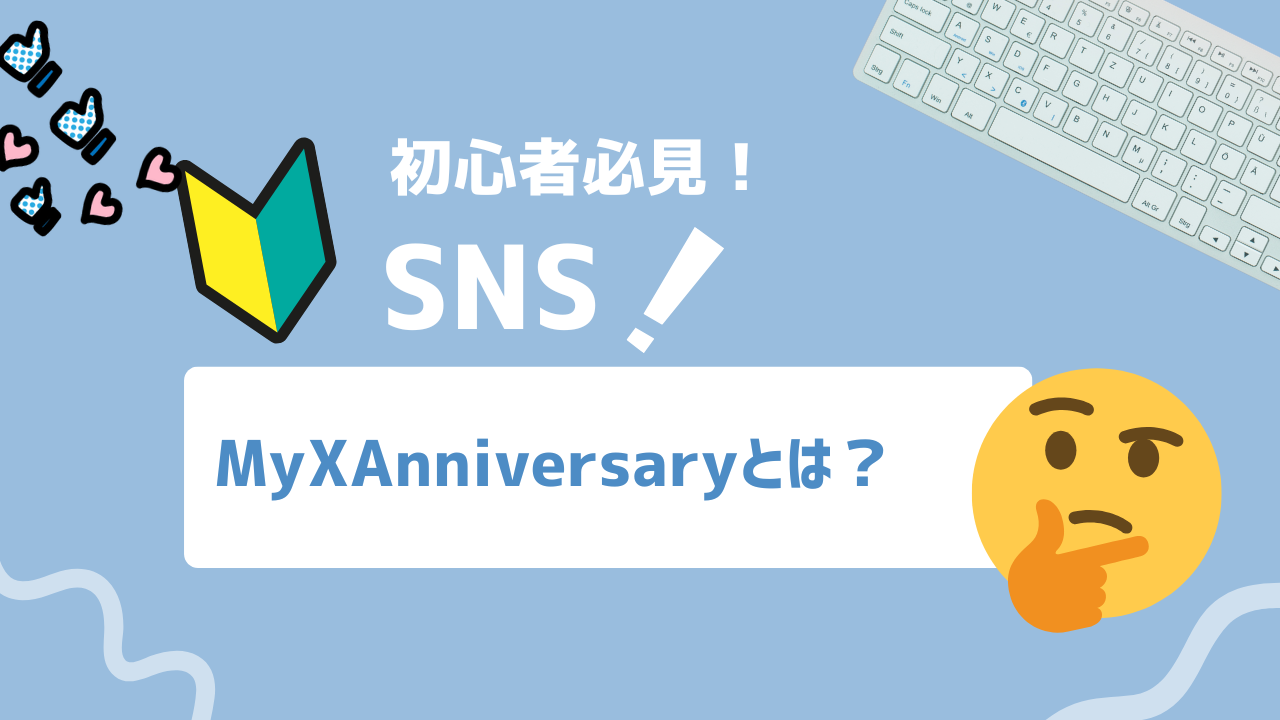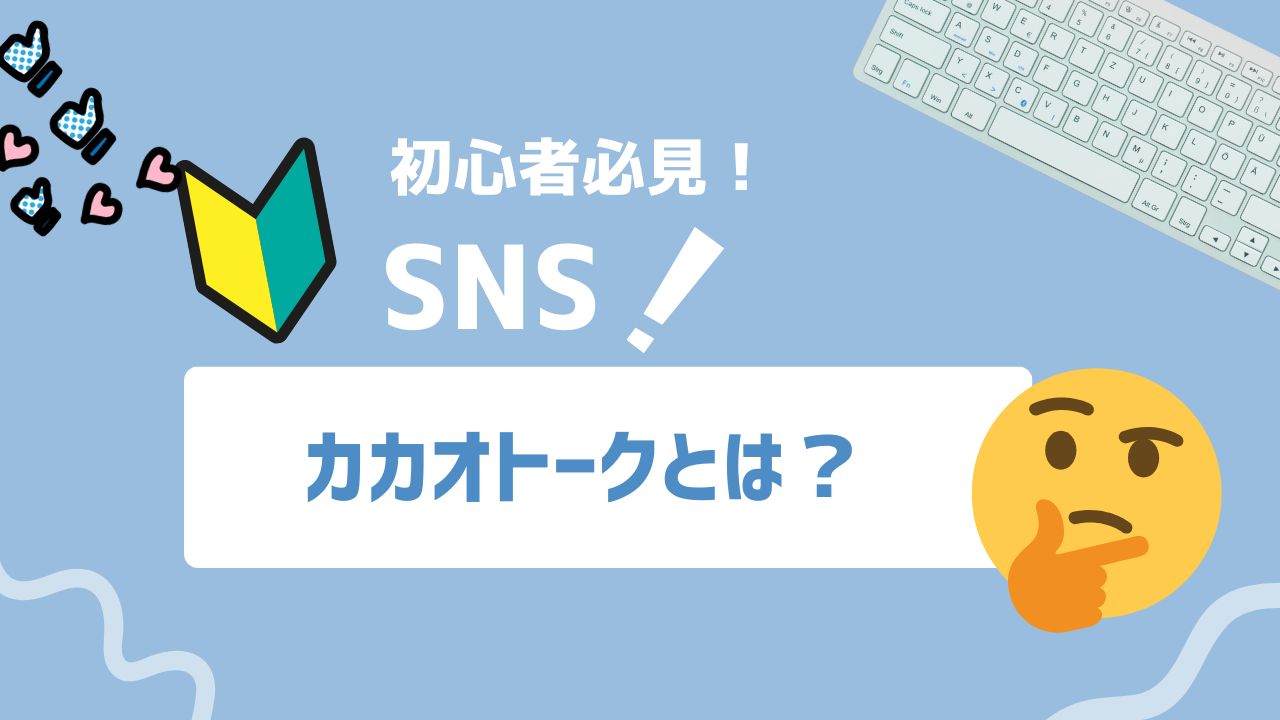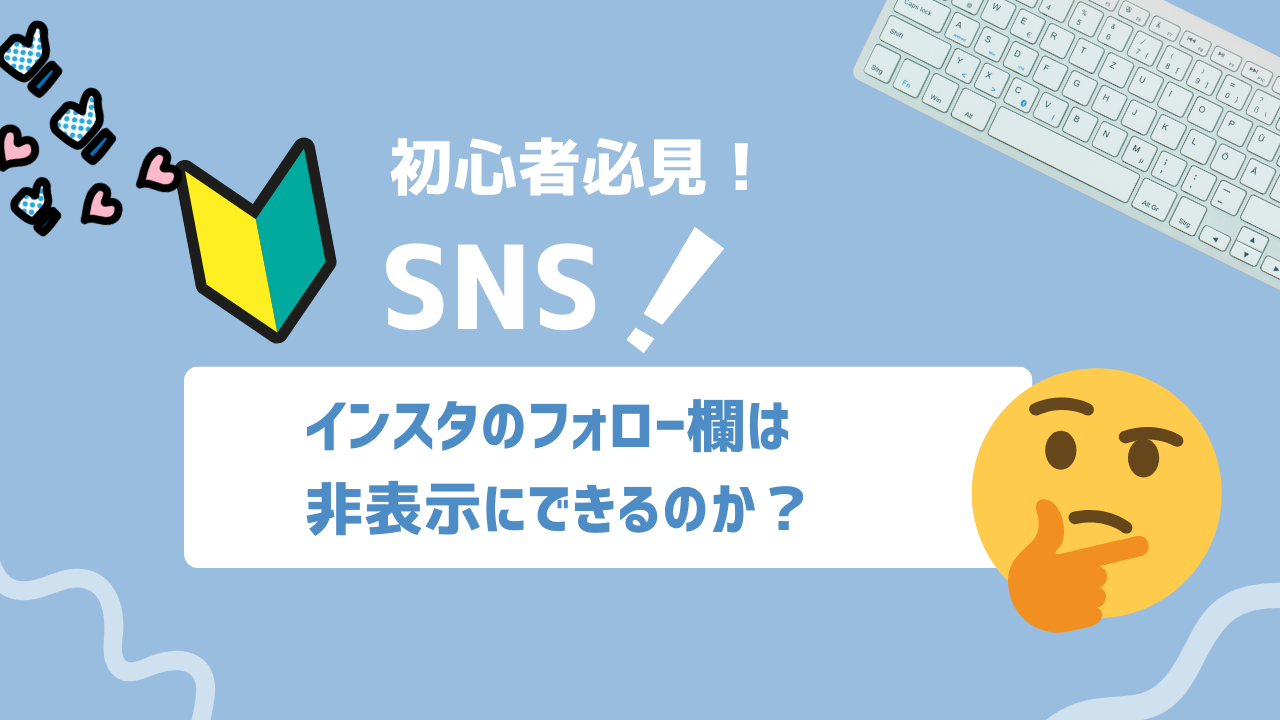【2025年最新】Xアカウント所在地表示とは?確認方法・仕組み・リスク対策を解説
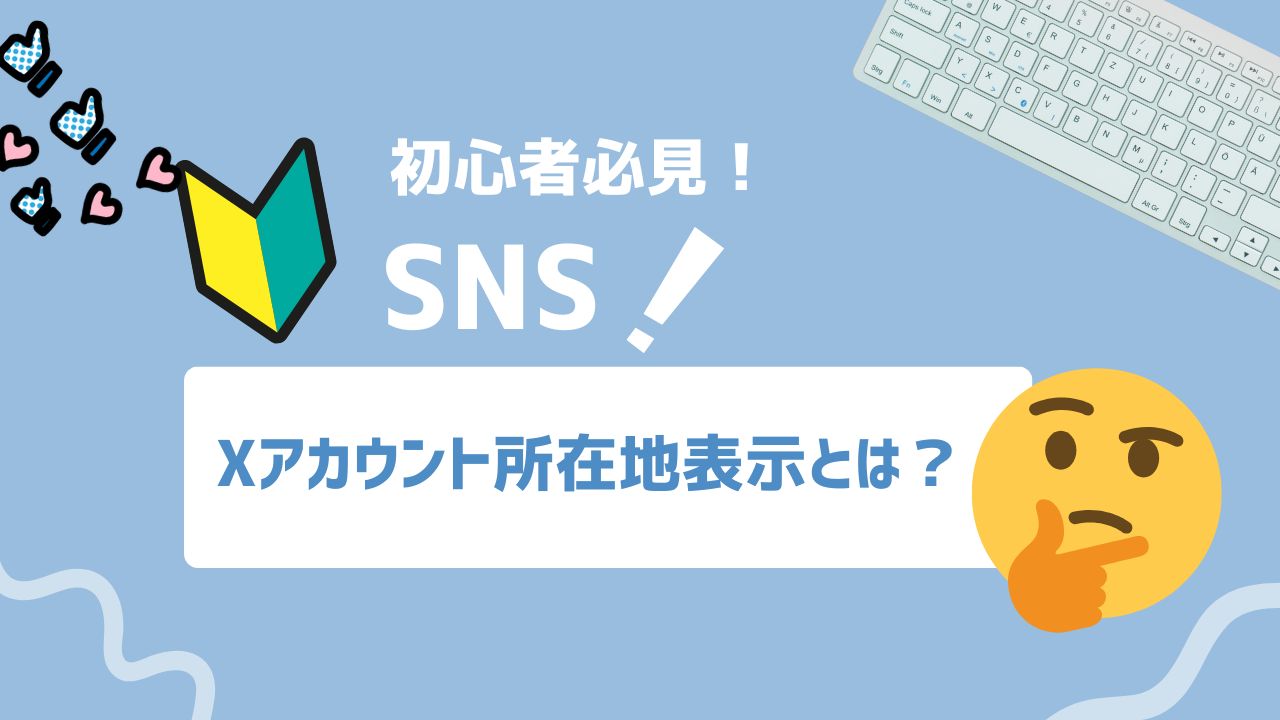
2025年11月にX(旧Twitter)で導入された「アカウントの所在地」表示。企業アカウントやインフルエンサーとのタイアップを担当していると、「ブランドイメージや信頼性にどこまで影響するのか」「担当者の居場所までバレるのか」「VPNを使っていても大丈夫なのか」など、気になるポイントが一気に増えたはずです。本記事では、この新機能の確認方法と仕組み、リスク、そして運用のポイントを整理します。
目次
Xアカウント所在地表示機能の概要と背景
Xのプロフィール画面には、これまで登録日や認証バッジの有無などの情報が表示されてきましたが、2025年11月から新たに「このアカウントについて」という情報パネルが追加され、その中に「アカウントの所在地」や「接続元」「ユーザー名の変更回数」などが表示されるようになりました。まずは、この機能がどのような情報を表示するためのもので、何を目的として導入されたのかを押さえましょう。
2025年に始まった「このアカウントについて」とは
「このアカウントについて」は、ユーザーのプロフィール画面からアクセスできる追加情報のことで、Xがアカウントの透明性を高めるために導入した機能です。ここでは、アカウントを作成した年月、拠点としている国・地域、認証バッジの有無と取得時期、ユーザー名(@ID)の変更回数、そして接続元の種類などが一覧で確認できます。Xのプロダクト責任者は「コンテンツの信頼性をユーザーが判断できるようにすることが重要だ」と述べており、国や接続元といった情報は、どこの誰が発信しているのかを判断するための手がかりとして位置づけられています。
表示される情報の種類と意味
「このアカウントについて」に表示される代表的な情報として、登録日、アカウントの所在地、認証済みバッジ、ユーザー名の変更回数、接続元の5種類があります。登録日は、そのアカウントがどれくらいの期間運用されてきたのかを示し、長期運用されているアカウントほど信頼度の判断材料になりやすくなります。所在地は「そのアカウントのユーザーがいる国または地域」を意味し、ブランドの実際の活動エリアとの整合性を見る指標になります。一方、接続元は「Japan App Store」「Japan Android App」「Web」のようなラベルで、主にどのデバイスや経路から利用されているかを示しており、所在地表示と混同しないことが重要です。
ボット対策・偽情報対策としての狙い
この機能の背景には、ボットや外国勢力による情報工作への対策という明確な文脈があります。Xは、拠点国の表示や接続元の情報を公開することで、匿名性が高すぎるアカウントや、国内発を装った海外発信を見分けやすくする狙いを持っています。日本政府も、海外からの偽情報拡散を含む影響工作の存在を公式に指摘しており、プラットフォーム側の透明性向上はこうした動きを抑制する一手として期待されています。
アカウント所在地はどう決まる?仕組みと限界
所在地表示は、一見すると「今アクセスしているIPアドレスの国名」で決まっているように見えますが、実際にはもう少し複雑なロジックで算出されていると考えられています。Xは具体的なアルゴリズムを公表していませんが、接続に使っている回線や利用可能な各種情報を組み合わせ、一定期間ごとに所在地を更新していると説明しています。
国設定・接続履歴・アプリストア情報の組み合わせ
所在地の推定には、Xに接続している回線の情報、利用しているアプリストアや端末の地域設定などが使われているとみられています。また、所在地はリアルタイムの位置情報ではなく、「利用可能な情報にもとづいて、最大30日以内の遅延・ランダム化されたスケジュールで更新される」とされており、表示されている国が常に最新とは限りません。そのため、短期の出張や一時的な接続変更だけで所在地がすぐ変わるわけではなく、あくまで中期的な傾向としての拠点を推定する仕組みになっています。
VPN・海外出張・複数端末利用で起こり得る誤差と「盾マーク」
推定ベースである以上、VPNやプロキシ、海外出張、外部のSNS管理ツールなどを組み合わせて利用しているアカウントでは、所在地表示と実際の拠点がズレるケースが発生します。特にVPNについては、所在地の右側に「盾マーク」が表示され、「プロキシやVPN経由の接続が推定されるため、表示される国は実際の所在地と異なる可能性がある」といった注意書きが示されることがあります。また、一部のスマホ端末はユーザーが意識しないうちにプロキシを利用していることもあり、ユーザー側から見ると「何もしていないのにVPN扱いになっている」という状況も起こり得ます。
「East Asia & Pacific」「Unknown」が意味するもの
所在地の欄には、必ずしも国名だけが表示されるとは限りません。安全上の理由から詳しい居場所を明かしたくないジャーナリストや活動家などは、国の代わりに「East Asia & Pacific」のような大まかな地域や大陸名を表示する設定を利用できるようになっています。この場合、所在地も接続元も同じ地域名で表示されることがあり、ユーザーからは「どこの国なのか特定しづらい」状態になります。また、推定に必要な情報が不足している場合には「Unknown」と表示されることもあり、これは意図的な非公開というより「システムが十分なデータを持っていない」状態と理解しておくと良いでしょう。
自社アカウントの所在地を確認・調整する手順(スマホ)
まず、自社の公式アカウントや関係者アカウントの所在地表示を確認してみましょう。ここではスマホアプリを前提に、どの画面から「このアカウントについて」にアクセスし、所在地や接続元をチェックするかを整理します。現時点では所在地そのものを自由に書き換える設定はないため、「どのように推定され、どう見え方を整えるか」を意識して運用することが大切です。
プロフィールから[このアカウントについて]を開く手順(スマホ)
Xアプリで、アカウントのプロフィール画面を開きます。プロフィール情報の少し下にある、「〇年〇月からXを利用しています」をタップします。

「このアカウントについて」パネルが開きます。その中に「アカウントの所在地」「接続元」などが表示されているので、自社アカウントの場合は、ブランドの活動拠点と矛盾していないかをチェックします。他社やインフルエンサーのアカウントを評価するときも、同じ手順で所在地と接続元を確認しておくと、コラボの信頼性判断に役立ちます。

設定画面で「国」と「地域/大陸」を切り替える
所在地自体を任意の国名に書き換えることはできませんが、「国名で表示するか」「地域・大陸名で表示するか」は設定から選択できます。
ホーム画面左側のメニューから「設定とプライバシー」を選択します。

「プライバシーと安全」→「アカウントについて」と進むと、「アカウント情報に地域または国のどちらを表示するかを選択できます」という画面が表示されます。


ここで「国を使用する」を選べば通常どおり「Japan」のような国名が表示され、「地域/大陸を使用する」を選ぶと「East Asia & Pacific」のような広い地域で表示されるようになります。



「完全にはコントロールできない」前提での調整のコツ
所在地は推定に基づき、最大30日ほどの遅延を伴って更新されるため、担当者の行動や回線環境を細かく調整しても、完全に意図した表示にできる性質のものではありません。そのため、調整の基本は「極端にズレた表示を避ける」ことにあります。例えば、日本のブランドの公式アカウントが、長期間にわたって海外のVPNサーバー経由でしか運用されていないと、所在地がその国になってしまうリスクが高まります。運用に使う端末やネットワークをある程度固定し、「少なくとも主要な拠点国とは一致している」状態を保つことが現実的な落としどころになるでしょう。
マーケティング・ブランド運用への影響と活用アイデア
所在地表示は単なる仕様変更に見えて、ブランドコミュニケーションに直接影響する要素です。ユーザーは、プロフィールに書かれた自己紹介だけでなく、「このアカウントについて」の情報も含めてアカウントの素性を判断するようになっていきます。ここでは、企業アカウント運営の観点から、所在地表示が生むリスクとチャンスを整理します。
プロフィールと所在地が食い違うときの不信・炎上リスク
プロフィールでは「日本発のブランド」と謳っているのに、所在地が海外になっている場合、ユーザーによっては「本当はどこが運営しているのか」「なぜ説明がないのか」と疑念を抱く可能性があります。特に政治・社会問題に関わるアカウントでは、拠点国の食い違いが炎上の火種になりやすく、一般ユーザーの間でも「言っていることと所在地が合っていない」と指摘される事例が出始めています。企業アカウントの場合も、広告やキャンペーンで「地域密着」を押し出しているのに所在地表示が別の国になっていると、ブランドストーリー全体への信頼を損ねかねません。こうしたギャップは「嘘」ではなくても、説明なく放置すると不信の温床になってしまいます。
インフルエンサー選定・タイアップ時のチェックリスト
インフルエンサーやクリエイターとタイアップする際、これまではフォロワー属性や投稿内容を中心にチェックしていた担当者も多いはずです。所在地表示が導入されたことで、「どの国を拠点に活動しているのか」「言っている拠点と表示される拠点が一致しているか」という新たな評価軸が加わります。同時に、VPN利用や地域設定の事情で一時的にズレることもあるため、「数日だけのズレなのか」「長期的に一貫しているか」を期間を置いて確認する視点も重要になります。コラボを検討する際には、少なくともキャンペーン開始前に一度、「このアカウントについて」のスクリーンショットを残しておくと、社内説明にも役立ちます。
公式アカウントガバナンスと「運用者の居場所」の扱い方
所在地表示が導入されたことで、「誰がどこから運用しているのか」という情報が、ある程度ユーザーに可視化されるようになりました。完全に個人の居住地が分かるわけではないものの、特定の国や地域からの運用が推定されるため、企業としてはガバナンスの観点からも運用ルールを整理しておく必要があります。たとえば、公式アカウントは原則として本社または主要拠点のネットワークから運用する、長期出張や海外駐在の担当者が運用する場合はプロフィールや固定ポストで一言説明を添える、といった方針です。所在地表示を前提にした「見せ方の設計」を行うことで、逆に「透明性の高いブランド」として信頼を獲得するチャンスにもなります。
VPN・海外在住で運用する際の実務的な注意点
グローバルに事業を展開している企業や、リモートワークが標準化している組織では、担当者が海外からXを運用するケースも珍しくありません。また、業務上のセキュリティ要件からVPN接続を必須としている会社も増えています。そうした環境下で所在地表示をどう扱うかは、現場の運用ルールとしてあらかじめ整理しておくべきポイントです。
VPN利用時の盾マークと注意文をどう捉えるか
所在地の横に表示される盾マークは、「このアカウントはプロキシやVPN経由で接続している可能性がある」と推定されている状態を示します。ユーザーがこのマークをタップすると、「表示される国または地域は変更される可能性があり、このデータは正確ではない場合があります」といった注意書きが表示されるため、一見すると怪しい印象を与えることもあります。ただし、VPNは企業のセキュリティ対策としても広く使われており、「VPNだから=不正」という単純な図式ではありません。企業としては、必要なVPN利用は維持しつつ、「なぜ盾マークが付くのか」を社内で共有し、説明が必要な場面では丁寧に伝えられるようにしておくことが重要です。
海外駐在・出張メンバーが運用する場合のベストプラクティス
海外拠点の担当者や長期出張中のメンバーが公式アカウントを運用する場合、所在地表示はその国や近隣地域になる可能性があります。これ自体は必ずしも問題ではありませんが、本社アカウントとして「日本市場向けの発信」をしているにもかかわらず、常に別の国が表示されていると違和感を持つユーザーもいます。実務的には、重要なカンファレンスやイベント期間だけ現地から運用する場合には、「期間限定で海外から発信しています」といった説明をポストする、もしくは固定ポストで運用体制を明示するのが無難です。長期的に海外チームが運用する場合は、「グローバルチームによる運用」であることをストーリーとして打ち出すことも検討できます。
所在地とプロフィールがズレるときの説明・注記の出し方
所在地表示は仕組み上どうしても誤差が出るため、プロフィールの自己紹介や固定ポストで補足することが現実的な対応策になります。たとえば、「日本発ブランド/チームは世界各地からリモートで運用中」といった文言で、所在地とブランドメッセージの両方を違和感なく伝えることができます。また、盾マークが付いている場合には、問い合わせが来た際に「社内ネットワーク保護のためVPN経由で接続しています」と説明できるよう、カスタマーサポートとの連携も含めて社内FAQを整備すると安心です。こうした一言の補足があるだけで、ユーザーの受け取り方は大きく変わります。
Xアカウント所在地表示に関するよくある質問(FAQ)
所在地表示機能はまだ登場したばかりで、仕様も改善の途上にあります。ここでは、現時点で判明している範囲と、今後のアップデート次第となる部分を分けながら、代表的な質問に答えます。
所在地表示はIPアドレスそのもの?どの程度正確だと考えるべき?
所在地表示は、単純に「今のIPアドレスの位置情報」をそのまま出しているわけではなく、接続に使っている回線や利用可能な情報にもとづいて推定され、最大30日ほどの遅延を伴って更新される仕組みです。そのため、短期の旅行や一時的な接続変更はすぐには反映されず、過去の利用履歴を含めた拠点としての国が表示されるイメージに近いと言えます。一方で、VPNや外部ツールを多用していると誤差が大きくなり、「アカウントの所在地が正確とは限らない」と公式にも注意されている点には留意が必要です。
所在地を完全に非表示にすることはできないの?
現時点では、一般的なアカウントの場合、所在地表示を完全にオフにする設定は用意されていません。例外として、テロ防止などの観点から、グレーのチェックマークが付いた政府・政治家アカウントでは所在地が表示されない仕様になっています。また、推定に必要な情報がほとんど得られない場合や、仕組み上うまく推定できないケースでは一時的に表示されないこともありますが、意図的に「何も表示させない」状態を選ぶことは基本的にできません。そのため、企業としては「表示される前提」でガバナンスやコミュニケーション方針を設計するのが現実的です。
所在地表示は広告配信やアルゴリズムに影響する?
所在地表示そのものが、広告配信のターゲティングやタイムラインの表示順位にどこまで影響するかは、現時点では明確に公開されていません。ただ、Xは「コンテンツの信頼性を判断するためのシグナル」として所在地や接続元の情報を重視していると発言しており、将来的に何らかの形でアルゴリズムに組み込まれる可能性は考えられます。一方で、広告配信においては従来どおりユーザー側の位置情報や興味関心データが中心であり、発信側アカウントの所在地だけで配信が大きく変わるとは考えにくいのが現実的な見方です。
所在地が頻繁に変わると「怪しいアカウント」に見える?
所在地が短期間で頻繁に変わると、ユーザーから「どこから発信しているのか分からないアカウント」という印象を持たれやすくなります。特に政治的・社会的なテーマを扱うアカウントでは、意図的な隠蔽やなりすましを疑われるリスクが高まります。企業アカウントの場合も、運用担当者がたまたま国内外を移動しているだけでも、文脈なく所在地が変わり続けると違和感を与えかねません。可能であれば、メインで運用する国やネットワークをある程度固定し、やむを得ず変化する場合には状況を説明する姿勢が望ましいでしょう。
まとめ
Xアカウントの所在地表示は、単に「どこの国からアクセスしているか」を見せるための機能ではなく、誰がどこから発信しているのかをユーザーが判断するための透明性向上の仕組みです。推定ベースである以上、VPNや海外出張などで誤差が生じることは避けられませんが、それを前提にプロフィールや運用ガイドラインを設計しましょう。まずは自社アカウントの所在地表示を確認し、必要に応じて説明や注記を整えながら、中長期のアップデートにも対応できる運用体制を整えていきましょう。
 ポスト
ポスト シェア
シェア